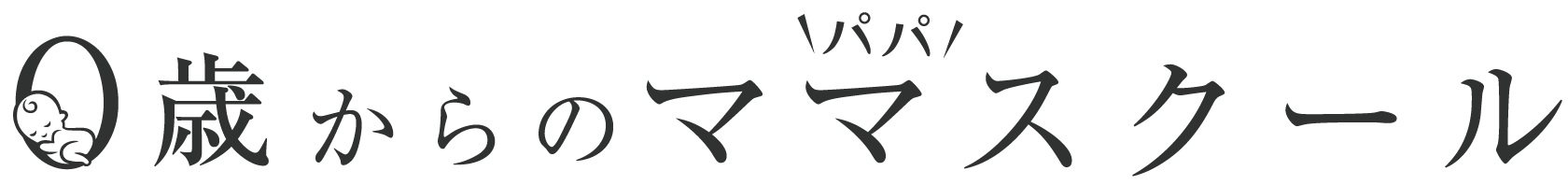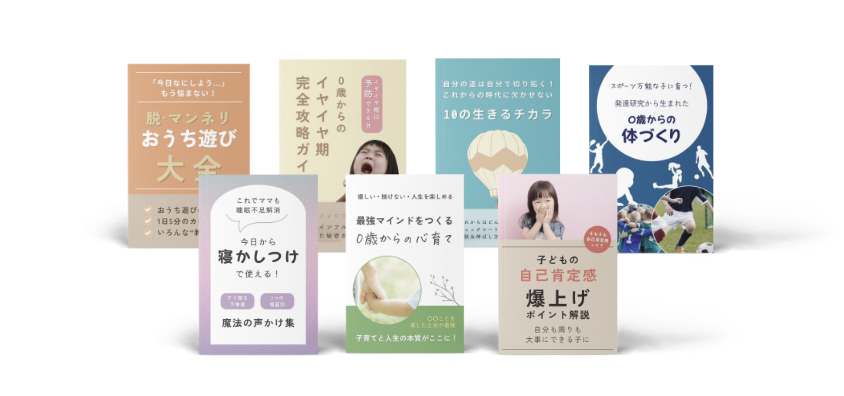子どもが数字を理解するのは何歳から?日常生活で数字の理解を進めるポイントも解説
情報が多すぎてどれが正しいのかわからず、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。 数字の理解には段階があり、0〜1歳の時点では、まだできていなくて当たり前です。さらに、数字を理解する時期に正解はないため、悩みすぎないことも大切です。 この記事では、数字の理解の発達の目安や日常でできる関わり方などを解説します。無理のない育児のヒントを見つけましょう。 目次 ・数唱 これらを順序立てて学んでいくことが大切です。また、バランスよく学ぶことで、数学的思考の基礎を身につけられるでしょう。それぞれ詳しく見ていきます。 数唱とは、数を順番に口頭で数えることです。 多くの場合、数を学ぶ最初のステップとなります。数の順序やパターンを理解するための基礎で、数の連続性や規則性を感覚的にとらえられるでしょう。 2〜3歳頃に、子どもは簡単な数唱を真似し始めますが、ただ唱えているだけで意味を理解しているわけではありません。しかし、繰り返すことで数字や数量の理解につながるでしょう。 4〜5歳頃、10や20までの数唱ができるようになり、順番のルールを理解し始めます。数唱を学ぶために、歌やゲームに数唱を取り入れることや日常生活で数を数える機会を作るなどを行いましょう。 一般的に数字の形がわかる時期は2〜3歳頃です。数唱ができれば、数字を見て数えられるようになり、理解が進んでいきます。また、始めは数字と数量の関連を理解していない場合があるでしょう。 4〜5歳頃には、数字とその意味を理解し始めます。数字カードや数字を使ったゲームなどを取り入れることや、日常生活で数字を意識させることで、数字の理解を進めることができます。 数量は物の量を表す数のことで、数の実用的な意味を学べます。また、足し算や引き算、比較などの基礎となるでしょう。 2〜3歳頃に、子どもは簡単な数量を認識し始めます。ただし、正確な対応は難しい場合があります。このとき、数唱や数字を用いて、理解を深めるとよいでしょう。 4〜5歳では、子どもは物と数を対応させる能力が発達し、正確に数えられるようになります。さらに、数量の比較や数の変化も理解できるようになるでしょう。 数量は、具体的な物を使うと理解を進めやすいです。例えば、おやつの数を数えることや、リンゴとミカンのどちらが多いかを尋ねるなどを行いましょう。 数の3つの要素を理解しても、実際に子どもに教えることはハードルが高く感じる方もいるでしょう。そんなママにおすすめなのが、おうちで1日5分、ママが遊び感覚で見せるだけで、子どもが数に強くなるドッツカードです。 ドッツカードは、世界で10万人以上が効果を実感したドーマンメソッドの取り組みのひとつで、生後3ヶ月半から子どもに見せてあげられるカードです。 白地に赤い丸が描かれており、数字をまだ知らない子どもだけが持つ特殊な能力を引き出してあげることができます。 代表的な効果は、以下が挙げられます。 ・ママが数学苦手でも、子どもは数に強くなる 知識をゼロから学んで実践できるように、プロの先生による相談会やママどうしのオンラインコミュニティ、Zoomでのお茶会などありそうでなかった赤ちゃんママさんが欲しいものが詰まった場を用意しています。 まずは効果や実践方法を知れる無料セミナーに参加してみませんか? ・0歳頃 子どもの数字の理解は、音やリズムから始まり、物との対応や数量の理解、応用へと進化します。日常生活の中で楽しく数に触れる機会を増やすことで、自然に理解が深まるでしょう。 それでは、それぞれの年齢ごとの発達を、詳しく説明します。 0歳頃では、数字の概念はまだありません。音やリズムを通じて数に触れる土台をつくりましょう。 例えば、数を含む歌や手遊びを行うことで、数の順序の音を耳で覚え始めます。発語が始まった際に、数唱の理解につながるでしょう。 また、数量の理解の一環として、おもちゃの数や大きさの違いに触れることがおすすめです。数に何度も触れることで、数が数えられたり、数が理解できたりするようになるでしょう。 1歳頃では、身近なものを数えるきっかけが生まれます。3までの数を中心に、遊びや日常生活で子どもと一緒に物の数を数えるとよいでしょう。 日常生活に取り入れて数唱を繰り返すことで、3までの簡単な数字の単語を聞き、真似して発音し始めるようになります。また、1歳頃は数の学習の強制は行わず、楽しく数を学ぶことが大切です。 2歳頃では、1〜3程度の数と対応づけが始まります。 数唱はもちろん、数量の理解も進んでいくでしょう。数字カードを用いて、数字の理解を進めるにも、2歳頃は適しています。 理解を深めるには、お菓子の数を数えることやおもちゃの数を数えることなど、日常生活や遊びに数を取り入れることが大切です。視覚的な刺激のほか、触覚的な体験も取り入れながら、数字を見たり聞いたり触ったりすることにより理解を深めましょう。 ただし、4以上になると混乱を招くことがあるので、子どもの様子を見て少しずつ進めていきましょう。 物を5までなら数えられることや、「増える」「減る」といった概念の理解が始まります。また、数字を書く子どもも出てくるでしょう。 このように、3歳頃になると、数の3つの要素の理解が深まります。理解を深めるには継続が重要で、子どもの興味や関心に合わせて数に触れるチャンスをあげましょう。 4歳頃になると、10までの数を扱え、簡単な計算や数の応用が始まります。5歳頃では、順序数や集合数も理解できるようになり、算数の学習の土台が作られます。また、6歳頃になると100までの数を数えられるようになるでしょう。 指を使った簡単な足し算や引き算、数の大小比較など、おやつやおもちゃなどを用いて子どもと学ぶとよいでしょう。 年齢ごとや個人による発達の差で、どのように数を教えてよいのか悩む方もいるのではないでしょうか。0歳からのママスクールでは、育児の土台を築くために必要な知識や方法を提供します。 スマートフォン1台で子育て方法がいつでも学べるオンライン上での動画版またはテキスト版の学習形態を完備しています。視聴期限もなく、ママが忙しい育児の合間でも学びやすいです。 また、ドーマンメソッドの一環としてドッツカードを日本で唯一販売権を獲得しており、遊び感覚で家庭で子どもの可能性を伸ばせる道具として活用できます。ドッツカードにより、生後3ヶ月半から遊び感覚で手軽に数の理解を深められるでしょう。 数だけでなく、子どもに何かを教えるには、悩む場面もあるでしょう。ぜひ無料セミナーを受けて、子育てを楽しむためのヒントを得てください。 普段から数字に触れるように意識する 子どもが数字を楽しいと感じる場面を増やして、具体的な物や行動を通じて数を体感させましょう。それぞれ詳しく説明します。 日常生活で数字に触れるためには、以下のポイントを意識しましょう。 ・数字を活用する場面を作る 楽しく数を学ぶために、日常生活で数の概念を教える必要があります。また、無理に教え込む必要はありません。子どもが楽しめる範囲内で行いましょう。例えば、以下の事柄を行います。 ・スーパーで買う物の個数を伝えて取ってもらう 数の概念を理解していなければ、実行が難しい場合があります。その場合でも、焦らずにゆっくりと教えるようにしましょう。 例えば、0〜2歳頃なら、お菓子を握らせましょう。このとき、握らせる量を変えて、多い少ないを教えると数量感覚を育むのに有効です。 3〜5歳頃なら、お菓子を分ける体験をしてもよいかもしれません。例えば6枚のクッキーを2人で分けるときに一人何枚になるのかを、実際に分けてみましょう。数を分け合う意味の理解につながります。 実際に数を体験してもらうときは、シンプルな数から始めることや、公平さや協力の楽しさがわかるようにする必要があります。また、子どもが間違えても、失敗を学びの機会にするために間違いを肯定的に扱いましょう。 日常生活でも、数の学習を行える場面は多々あります。0歳からのママスクールのベースのドーマンメソッドを学べば、子どもに自分で考えて行動する力を身につけてあげられるでしょう。 さらに、ほかのママたちとオンラインで交流できる場を提供しています。コミュニティ内で悩みを共有し、一緒に学びながら育児を楽しむことが可能です。 また、運営から公式に認定されたサポートママさんが返信を行うこともあります。 同じママ仲間とつながりながら育児を行えば、不安や負担が軽減されるのではないでしょうか。ぜひ無料セミナーを受けて、子育てを楽しむためのヒントを得てください。 楽しみながら数字を覚えられる遊びは、いくつかあります。 ・トランプ 数字の学びは遊びの延長で、子どもが自然に楽しめるように進められます。それぞれ詳しく見ていきましょう。 トランプは、数字や順序を学ぶことに適しています。シンプルなルールで、楽しみながら算数の基礎を身につけられるでしょう。 3歳頃からは数字を認識できるババ抜きや七並べなどを行いましょう。もちろん、難しい場合もあるため、子どもの様子を見ながら楽しめる工夫が必要です。 4〜5歳頃になると、カードの数字を足して10になる組み合わせを探すゲームを行ってもよいでしょう。数そのものを理解するだけでなく、足し算の概念の理解にもつながります。 また、神経衰弱なら、数字の認識だけでなく記憶力を養うことにもつながります。すべての枚数で行うことは難しいため、幼児でも行えるように枚数の調整がおすすめです。 学びのポイントは、サイコロの目を数え1〜6の数字を覚えることや、マスの移動により数の大小や順番が体感できることなどです。 実際に、未就学児を対象に数列ボードゲームを行った研究では、2週間の活動により数的知識の向上が9週間後も継続したことが報告されています。 5マス進む、3マス戻るなどの足し算や引き算の要素もあるすごろくは、楽しみながら数を学ぶことに適しているでしょう。 数字カードはトランプと似ている数が書かれたカードです。しかし、トランプよりシンプルなため、幼児向けに特化しているものがほとんどです。 幼児と遊ぶときは、数字を見て数唱を行うことや数字を順番に並べること、数字の大小を比べることなどを行うと効果があります。楽しみながら学習を進めましょう。 絵本ではストーリーやイラストから、数字を楽しく学べます。数への関心を高めるポイントは、以下のとおりです。 ・絵本をいつでも読める環境作り 学習を感じさせず、話を楽しみながら自然に数が身につきます。また、読み聞かせを行うことにより、数の学習だけではなく親子の結びつきも強まるでしょう。 ・童謡を歌いながら数字の名前と形を学べる 数字の3つの要素を、遊びながら楽しく学べます。また、幼児でも数の概念を簡単に学ぶことができるでしょう。さらに、小学生に必要な算数の学習にも使えます。 遊びながら数を学ぶ方法はいくつもありますが、ドッツカードの使用もおすすめです。ママスクールでで使われているドッツカードは研究所が開発した日本で唯一の正規教材です。 カードのサイズや色合いも、赤ちゃんの発達に合わせて調整されており、市販されている一般的な教材とは一線を画します。 ママスクールは、ドッツカードを開発したドーマン博士と長年、一緒に活動されてきた先生が監修しており、教材と活用法の両面からママがおうちで子どもに数の土台づくりができる環境を用意しています。 気になる方は、まずはお気軽に無料セミナーをご利用ください。 通常、1〜4歳頃は、基礎を育てるために、以下のような方法が紹介されています。 ・物の数を理解する これらを、子どもの理解度に合わせて進めることができます。 さらに、学習にはそろばんやおはじき、ブロックなどを活用して視覚的に理解を促す方法もあります。 しかし、こうした内容を子どもに教えるのに高いハードルを感じる方も多いのではないでしょうか。 ママスクールで推奨しているドッツカードを活用すれば、0歳から親が1日5分、おもちゃ感覚でカードを見せてあげるだけで、子どもは楽しく足し算や引き算を理解できるようになっていきます。 そんなドッツカードの効果をもっとも得られるのは、子どもが数字を認識する前の時期までです。 まだ数字を知らないお子さんには、数を感覚的に理解できる大きなチャンスが目の前にあります。 ・発達段階に合わせて進める 数の概念は一朝一夕で身につくものではなく、毎日の積み重ねが必要です。また、達成感により学ぶ意欲が向上するため、子どもが理解したときはしっかりと褒めましょう。 また、無理に教え込む必要はありません。日常生活や遊びを通して、数に対する興味を引き出す必要があります。楽しいことを知れば、子ども自ら学ぶようになるでしょう。 それでもやはり、子どもへの数字の教え方に迷うこともあるでしょう。この記事を読んで理解は深まったものの、もっと具体的に相談したいと感じた方は、プロへの相談をおすすめします。 0歳からのママスクールはドーマンメソッドを知り尽くした幼児教育のプロが監修し、ママもお子さまも幸せになれる子育てをサポートするサービスです。 心・体・脳の3つを育めるドーマンメソッドをベースに子どもの一生分の土台づくりができる正しい知識だけにとどまらず、ママが楽しく幸せに子育てができるような親としての土台づくりに必要な知見や心がまえも提供しています。 さらに、ママが数学苦手でも子どもは数に強くなれるドッツカードの活用法など、子どもの可能性を伸ばしてあげられるコンテンツがママスクールにはあります。 そんなママスクールは現在、ドッツカードの効果や使い方、注意点をわかりやすく解説するオンラインセミナーを無料で開催しています。 まずはママスクールの無料セミナーに参加してみませんか?
「周りの子はもう数を数えているのに、うちの子はまだ……」「早いうちから何かした方がよいのかな」などと、子どもが数字を理解する時期に漠然とした不安を感じている方も少なくはありません。子どもが数字を理解するために必要なことは?

数字の理解には、以下の3つの要素があります。
・数字
・数量数唱
数字

数字は数を記号として示し、数の概念を具体化する役割があります。数字の認識は、算数や数学の学習の基礎につながります。数量
・子どもの理解力が高まる
・思いやりの心や好奇心を育める子どもが数字を理解するのは何歳から?

子どもが数字を理解するのは、どのくらいからなのでしょうか。以下に分け、年齢ごとの発達の目安をわかりやすく解説します。
・1歳頃
・2歳頃
・3歳頃
・4歳以降0歳頃
1歳頃
2歳頃
3歳頃

3歳頃になると、1〜5程度の数を理解して、簡単な計算の基礎が育ちます。4歳以降
日常生活で数字の理解を進めるポイント

日常生活で数字の理解を進めるには、特別な準備や教材がなくても進められます。その中でも、シンプルな方法を紹介します。
おやつなどを分けてみる普段から数字に触れるように意識する
・数字に関する質問を行う
・数量の理解を促す
・ブロックで積む個数を伝える
・絵本で物や動物の数を数える
・料理のお手伝いで個数に関する指示を出すおやつなどを分けてみる

おやつを分けることは、子どもが特に分配や等分などの数の概念を理解する機会になります。視覚だけでなく具体的な物を使う触覚の刺激により、数字と現実の関連を体感できます。楽しみながら数字を覚えられる遊びは?

数字を教えることが勉強になってしまうのではないかと心配している方もいるのではないでしょうか。できれば、子どもに無理をさせず、楽しく学ばせたいですよね。
・すごろく
・数字カード
・絵本
・スマートフォンアプリトランプ
すごろく

すごろくはサイコロの目やマスの数を数えることで、数字の学習を行えます。数字カード
絵本
・毎日数分間、絵本の読み聞かせの実施
・子どもと一緒に絵本を読むスマートフォンアプリ

スマートフォンアプリは、インタラクティブで視覚的な学習が可能です。例えば、以下のようなことを行えるアプリがあります。
・数字学習で1〜10まで数えながらなぞり書きをする
・形や色の認識などを育める
・大・小などものの大きさも身につける足し算や引き算は何歳頃できるようになる?

計算は早くからできないと遅れるのではと、焦りを感じている方もいるのではないでしょうか。足し算や引き算は5歳前後で自然に理解が進むため、焦る必要はありません。
・数字を理解する
・足し算の基礎となる数の合成を学ぶ
・掛け算や割り算の仕組みを理解する
・+や=など、式の記号を理解する
・足し算の答えを出す
・式を作成する子どもに数を教える際の関わりで大切なこと

子どもに数を教えるときは、褒めることや無理に覚えさせないこと、楽しい雰囲気を作ることが重要です。数字を教える際には、以下の点を押さえましょう。
・親子のコミュニケーションを通じて学ぶ
・子どもの反応を見て内容を決める
・日常の会話に数を取り入れる子どもへの数字の教え方に迷ったら

この記事では、子どもが数字を理解するための発達段階をわかりやすく解説し、日常生活の中で自然に数字に親しめるポイントや遊びを紹介しました。