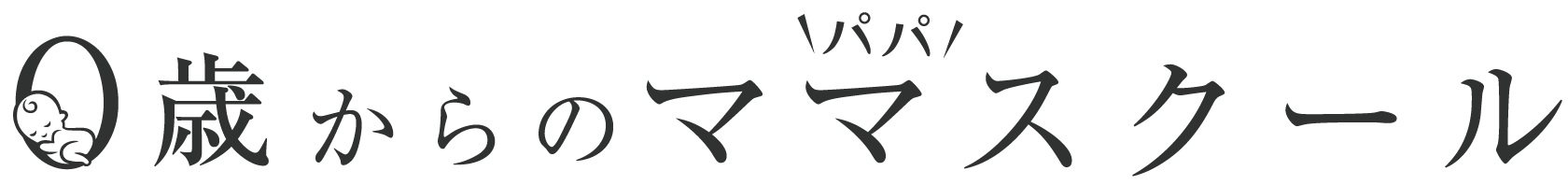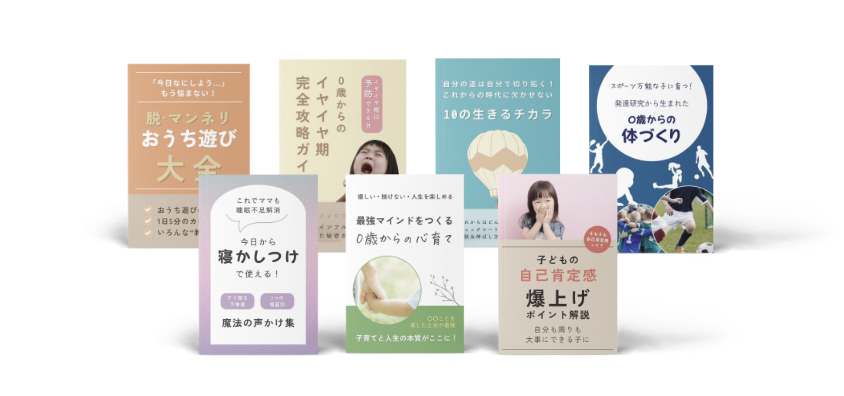集中力のある子どもに育てる方法は?子どもの集中力の特徴や集中できない原因を解説
しかし、子どもの集中力は脳の発達過程によるため、年齢に応じて大きな差があります。 集中力をつかさどる前頭前野は20歳代になってようやく完成する部分であり、今は集中が続かなくても自然なことなので、あまり心配しなくて大丈夫です。 本記事では、子どもの集中力の特徴や子どもの集中力が続かない原因などから、集中力のある子どもに育てる方法を紹介します。 子どもの集中力の正しい知識や伸ばし方をチェックして、できることから実践していきましょう。 目次 子どもが小さいうちは些細なことでも、できたかできないかが気になり、SNSで必死に情報を集めることもあるでしょう。 小さな子どもの脳は、急速に発達しますが、その発達過程は一律ではなく、遺伝子と育つ環境の影響を受けるほか、特に子どもの年齢が小さいうちは月齢でも大きく差が生じます。 そのため、短い時間であっても集中して何かに取り組めれば十分成長している証拠ですので、あまり心配しなくて大丈夫です。 集中力が続かないからダメなのではなく、年齢によっても大きく左右される部分なので、ほかの子どもと比べる必要はありません。 また、子どもの集中力は大人のように長時間続かないため不安に感じるかもしれませんが、子どもには大人とは異なる集中パターンがあります。 科学的な根拠はないものの、子どもが集中できる時間は、年齢+1分程度といわれています。思ったより短いと感じた方も少なくないでしょう。 子どもは大人が想像しているよりもはるかに集中力が続かず、1歳の子どもなら2〜3分でも集中して取り組めば十分です。 大人が集中してほしいと感じている時間と子どもが集中できる時間には大きなずれがあると認識しましょう。 例えば、5分間集中してもらいたいと考える場合には、1分×5回で合計5分としてみましょう。 飽きっぽいと感じる子どもでも朝からずっと観察してみると、集中して遊んではやめて、集中して遊んではやめてを繰り返しているケースもあります。 子どもが夢中になって遊んでいるときには、周囲がうるさくても名前を呼ばれてもまったく気付かないことも少なくありません。 子どもはたとえ短時間でも、深い集中力を発揮していることがあります。 深く集中して物事に取り組むと脳は急激に成長し、やりきった経験は将来的に新しいことに挑戦する原動力となります。 仮に飽きっぽいと感じる子どもでも、深く集中する時間が少しでもあれば、温かく見守ってあげましょう。 子どもの成長には個人差があり、集中できる時間や興味のあることもさまざまです。周囲の子どもと比べて一喜一憂することで、ママ自身も疲れてしまいます。 子育てを心から楽しむためにも、ママ自身が周りと比較せずに、目の前のお子さんの小さな成長に目を向けることが大切です。 ママスクールは、0歳からの一生分の心・体・脳をバランスよく育むドーマンメソッドをもとに、ママ自身がまず幸せに子育てできる子育ての知見を提供しています。 また、専門家と相談ができる場もある子育て相談会や同じ月齢のお子さんを育てるママと交流ができるオンラインコミュニティに参加できるなど、ママの心を豊かにできる環境も整えています。 子育てに不安を抱えてSNSで情報を探して時間を浪費する前に、まずはママスクールの無料セミナーに参加してみませんか。 大人になれば多少体調が悪かったり興味がなかったりしても、ある程度の集中力を維持できますが、子どもは違います。 子どもの集中力が続かないさまざまな原因を理解し、子どもの集中力が続く環境を整えることが大切です。 子どもは興味や関心がないことには集中できないどころか、見向きもしない子どももいるでしょう。 子どもの興味や関心のあるものを探すために助けになるのが多重知能理論とよばれるもので、人間のもつ知能は8つに分類されます。 ・言語的知能(ことば) 本が好きな子どもでも、数字がたくさん出てくる本に興味を示す子どももいれば、ことばの少ないカラフルな本が好きな子どももいます。 体を動かすのが得意な身体運動的知能に長けている子どもは、本をじっと読んだりひとりで黙々と作業したりするのが苦手かもしれません。 本をじっと読めない子=落ち着きのない子ではなく、外で体を動かす遊びなどほかに集中できることがひとつでもあれば、その子らしさとして温かく見守ってあげましょう。 また、落ち着きがないように見える子どもは、目の前にあるさまざまなものに興味をもてる好奇心旺盛な子どもかもしれません。 自分の子どもの興味や、関心のあるものをたくさん見つけて揃えてあげてみてください。 健康状態に問題のない子どもでも集中力が続く時間は年齢+1分といわれているため、体調の悪いときに集中力を発揮するのは難しいでしょう。 また、子どもの睡眠不足は深刻な問題とされており、睡眠不足が続くと脳や体の発達に悪影響があります。 体調が悪いときには無理せず休むことも大切ですが、日頃から睡眠不足に十分気をつけて体調を整えてあげましょう。 ストレスは、集中力をつかさどる前頭前野に影響をあたえて、一時的に機能を弱めることがわかっています。 人前でのスピーチや恐怖体験などで、頭が真っ白になり何も考えられなくなった経験をもつ方もいるでしょう。 人間にはストレスがかかるとストレスから逃げようとする力が働き、ストレスがなくなれば本来もっている力を発揮できるようになります。 子どもが集中できていないと感じている場合には、部屋の環境や洋服のしめつけ、お腹がすいていないかなどを見直してストレスをとりのぞいてあげましょう。 ストレスにも似ていますが、集中しにくい環境では、子どもは集中できません。 静かな環境を好む子は音がうるさい場所では集中するのは難しいため、静かな部屋を用意する必要があるでしょう。 日頃から子どもが集中できる環境を整えるためには、部屋の中をなるべくシンプルに保つことが大切です。 ものが乱雑に置かれていると脳に余計な情報が送られて、周りのものが気になって集中しにくい環境が生まれるため、集中してほしいときだけでも身の回りを片付けましょう。 しかし、育児や家事など目の前のことで精一杯で、子どもの将来のために何かを始める時間がない親御さんも少なくありません。 そこで、子どもの集中力を高めるための3つの方法を紹介します。親子でできることを少しずつ取り組んでみましょう。 おもちゃを積み重ねたり小さな虫を捕まえたりするなどの達成感を得られると、脳が活性化します。 小さくてもよいので、成功体験をたくさん積み重ねると脳が活性化されてモチベーションがあがり、集中力が高まります。 また、1歳半をすぎる頃から自分でなんでもやりたがるようになり、途中で手伝おうとすると激しく泣かれた経験をもつ方もいるでしょう。 子どもに小さな成功体験をさせてあげるために、ときには離れたところで見守り、できたときにはたくさん褒めてあげることが大切です。 疲れてくると目の前のことに集中できなくなるのは、誰しも経験のあることでしょう。 疲れて集中できていないなと感じたときには、適度な休憩を入れて脳を休めることも必要です。 ゆっくり休んでリラックスして副交感神経が活性化されると、集中力をつかさどる脳の血流がよくなり、また集中して取り組めるようになります。 生まれたばかりの赤ちゃんでも感覚系の機能は敏感です。手足を触って刺激したり、ものを舐めて感触を味わったりすることで、脳がどんどん発達していきます。 年齢+1分を目安に集中できる遊びを通じて、日常的に集中力を鍛えるトレーニングが必要です。 ただ、トレーニングが大切といわれても具体的に何をすればよいかわからない方もいるでしょう。 まずは、お子さんのことを一番理解している親が主体となり、家庭で実践ができるドーマンメソッドで親子の絆を深めてママ自身が幸せを感じられる子育てを体感してみませんか。 ドーマンメソッドとは、学ぶことを楽しむ土台づくりができる取り組みや運動神経を伸ばすオリジナルプログラムで構成されている、0歳から子どもの可能性を伸ばせる知見が詰まったメソッドでママスクールで学べます。 ほかにも子育てで大切なママの心を豊かにするママ同士がつながれるオンラインコミュニティや、専門家と相談ができる場を設けたオンライン相談会などのサポートも充実しています。 無料セミナーも随時開催しているので、子どもの可能性を広げるプログラムに興味のある方はぜひ参加してみてください。 ただ、親としてどのように子どもに関われば集中力アップにつながるのか、わからない方も少なくありません。 子どもの集中力アップのために親ができることを紹介するので、できることから取り組んでみましょう。 集中力アップのためには脳の発達が重要ですが、まず笑いやスキンシップを伴う遊びで、親子の基本的な信頼感をはぐくみましょう。 生まれたばかりの赤ちゃんでも感覚系の刺激には敏感なので、お腹をくすぐって笑ったりこまめなおむつ替えで不快な状況をよくしたりすると、親子の絆が深まります。 子どもにとって親が信頼できる基地になっていれば、子どもなりに周りの環境へ積極的に興味を示し、ますます脳が刺激されて発達していきます。 子どもが喜ぶ遊びを一緒に楽しみ一緒に笑い、たくさんスキンシップを取りましょう。 子どもの集中力をアップさせたいなら、身の回りを片付けて部屋をなるべくシンプルに保ちましょう。 しかし、毎日家事や育児に追われていると、部屋全体を片付ける時間が取れない方もいるかもしれません。 集中力アップのトレーニングを始めるときだけでも、周辺にあるほかのおもちゃを片付ければ、子どもは集中しやすくなります。 とはいえ、子どものためにしてあげたいことは多いものの、毎日家事や育児に追われ思うようにできないと落ち込んでしまうこともあるでしょう。 また、「3歳までは大切」ということを耳にし、不安に思う方もいるかもしれません。子どもの成長は一人ひとり違うので焦らなくても大丈夫です。 ママスクールでは、正しい子育ての知識をノウハウを提供し、ママ自身が幸せに子育てできる秘訣を楽しく学べます。 世界100ヶ国以上で50年以上にわたる研究から生まれたドーマンメソッドをもとにした専門的な知見を通して、お子さんの心・体・脳を育む一生分の土台づくりができるようになります。 ドーマンメソッドはおうちで1日5分あれば実践できるため、忙しい方や家事育児に追われている方でも取り入れやすいでしょう。 まずは無料セミナーから、おうちで手軽にできるドーマンメソッドにふれてみませんか。 子どもの脳の発達過程には順番があり、焦ってトレーニングをすすめてしまうと、かえって逆効果となる可能性もあります。 子どもの集中力を養うための3つの注意点を確認していきましょう。 子どもが嫌がることや興味のないことの無理強いは逆効果なので避けましょう。 脳の成長は感覚や動作などの基本的な機能から発達し、次に空間知覚・言語、さらに集中力や注意力などの高度機能へと続きます。 子どもの成長には個人差があり、興味のあることも子どもによってさまざまです。 親のやってほしいことを押し付けたり興味のないことを無理強いしたりせずに、子どもが笑顔になれることから始めていきましょう。 少し離れたところにあるおもちゃがほしいときに、取って渡してあげるのは簡単ですが、自分で試行錯誤して取りに行く挑戦も大切です。 正しいおもちゃの遊び方を教えるよりも、偶然鳴った音や形の変化に驚いたり面白さを感じたりして、子どもなりにおもちゃの遊び方を発見するのもよい経験になります。 すぐに答えを教えるのではなく、子どもの興味や好奇心をかき立てる工夫をしてあげることが大切です。 怪我をするような危ない遊びでない限り、ルールと違う遊び方をしていても叱らずに見守ってあげましょう。 子どもは成長していくにつれて、自分のやりたい遊び方と社会的なルールで禁止されていることを少しずつ学んでいきます。 しかし、子どもが萎縮してしまうほど叱ってしまうと、自発的なイキイキとした遊びをおそれて集中できなくなってしまいます。 集中しているときは多少の間違いは叱らず、子どもの集中力を見守ることも必要です。 叱らず見守ることが大切ですが、どの程度まで叱ってよいのか、叱ってしまった後の対応などに悩むこともあるでしょう。 ママスクールでは、本質的な知見で一生分の土台づくりのできる育児メソッドをもとに、正しい子育ての知識を提供しています。 赤ちゃんの数学的センスを開花してくれるドッツカードを使用し、ママが先生となり1日5分で手軽に実践しながらお子さんの可能性を広げることも可能です。 ドッツカードの基本的な使い方から効果的なコツ、注意などを無料オンラインセミナーでお伝えしております。セミナーはスマホ1台で参加できます。 ママ自身が幸せに子育てする秘訣や具体的な方法を学んでみませんか? ただ、自己流で行うことに不安を感じる方や子どもの集中力に焦りのある方は、信頼できる専門家のサポートを受けてみるのがおすすめです。 ママスクールは、心・体・脳を育むドーマンメソッドをもとに、0〜3歳の子どもを育てる秘訣を楽しく学べます。 知るだけで子育てに対する意識が変わる無料のセミナーも随時開催されており、子どもの可能性を広げるヒントが見つかるでしょう。 また、育児の悩みや不安を専門家に直接相談できる場もある子育て相談会や、ほかのママ同士とも交流できるオンラインコミュニティなども充実しています。 子どもの可能性を広げる秘訣を知りたい方は、まずは無料セミナーでママも子どもも幸せになるドーマンメソッドにふれてみてはいかがでしょうか。
「うちの子は落ち着きがない」「ほかの子と比べて集中力がない気がする」と悩む方もいるでしょう。子どもの集中力は年齢による

「ほかの子と比べてうちの子は集中力がないのかも」と不安に感じる親御さんは少なくありません。子どもの集中力の特徴

脳の大きさは3歳頃までに大人の約80%になるといわれていますが、集中力や高度な機能をつかさどる前頭前野はゆっくりと成長し、20代頃にようやく完成します。集中できる時間は年齢+1分
それても再び集中モードになる

子どもはごく短時間しか集中できないかわりに、注意力がそれても再び集中モードになります。短時間でも深い集中力
子どもの集中力が続かない原因

子どもの集中力が続かないと、自分の子どもに何か問題があるのではないかと考える親御さんも少なくないでしょう。興味や関心がない
・論理数学的知能(数字・量)
・音楽的知能(音楽)
・身体運動的知能(スポーツ)
・空間的知能(パズル・図形)
・対人的知能(人とのふれあい)
・内省的知能(ひとり作業)
・博物的知能(特定のものを深掘り)体調が悪い

熱があったりお腹の調子が悪かったり、誰しも体調の悪いときには集中力は続きません。ストレスがある
集中しにくい環境
子どもの集中力を高める方法

子どもの脳の発達は、遺伝と環境の2つの要因が影響します。遺伝は仕方のない要因ですが、環境は変えようと思えばいくらでも変えられる部分です。小さな成功体験を積み重ねる
適度な休憩を入れる
日常的にトレーニングする

小さな成功体験を積み重ねるのと同様に、日常的にものごとに集中するトレーニングを続けると、少しずつ集中力が養われていきます。子どもの集中力アップのために親ができること

小さな成功体験を積み上げたり日常的にトレーニングしたりすると、子どもの集中力アップにつながります。子どもが喜ぶ遊びを一緒に楽しむ
集中しやすい環境を整える

散らかっていたり音がうるさかったりすると、子どもはひとつのことに集中できず注意力散漫になりがちです。子どもの集中力を養うための注意点

少しでも早く落ち着いて集中できるようになってほしいと願うあまり、気持ちが強くなり焦ってしまうこともあるでしょう。無理強いは逆効果
すぐに答えを教えない

子どもが疑問にもったことの答えを教えるのは簡単です。しかし、すぐに答えを教えてしまうと、子どもは考えることをやめたり興味を示さなくなってしまう場合もあります。叱らずに見守る
子どもの集中力を育てたいなら

子どもの集中力を育てたいなら、集中できる環境を整え、子どもの興味を引き出すものを揃えて見守ることが大切です。