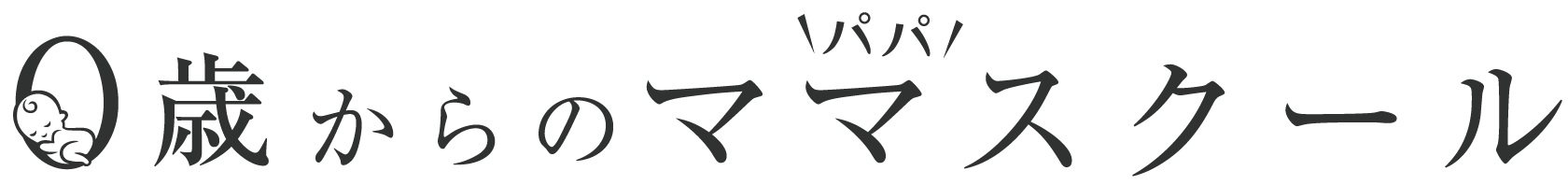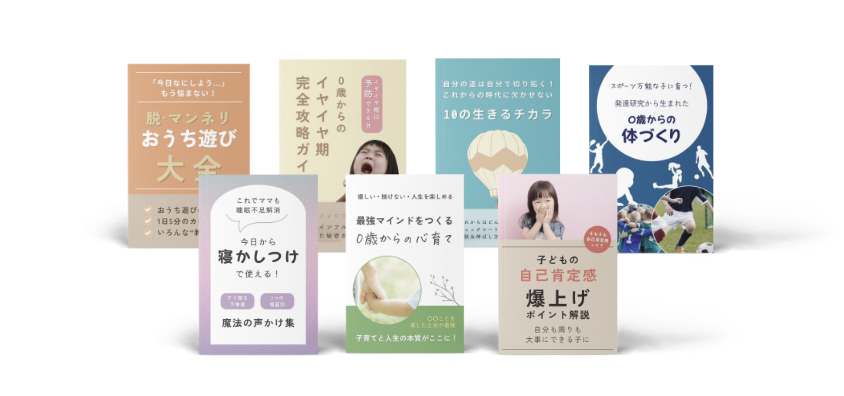2歳になるとできること|2歳児の発達の目安や遅れが気になる場合の対処法を解説
特に2歳前後は、言葉や体の動き、感情表現などが一気に発達する時期です。そのため成長のスピードに差が出やすく、子どもの発達に遅れがあるのではないかと心配になりやすい時期でしょう。 この記事では2歳児にみられる一般的な特徴や身体発育の目安、発達のチェックポイントを整理し、家庭で取り入れられる関わり方や発達に不安を感じたときの相談先について解説します。 子育て中の不安を軽くするきっかけにしていただければ幸いです。 目次 厚生労働省などの発達の目安によると、2歳児には次のような特徴が見られます。 言葉の面では「ママ」「ワンワン」などの単語が増え、「ママ、だっこ」のような二語文が少しずつ出るようになります。まだ発音がはっきりしていないこともあり、大人が聞き取れないこともありますが、自分の意思を言葉で伝えたい気持ちが強まっていく時期です。 運動面では安定して歩けるようになり、短い距離を走ることもできるようになります。段差の昇り降りやジャンプ、ボールを蹴るなどの動きに挑戦することも増えてくるでしょう。手先も器用になり、積み木を重ねたりスプーンやフォークを使って食事をしたりできるようになります。 また、自我が芽生えるためイヤイヤ期と呼ばれる行動も見られるようになります。自分でやりたい気持ちが強く、思い通りにいかないと泣いたり怒ったりすることが増えていきます。社会性の面では他者に興味を持ち、並んで同じ遊びをする平行遊びが見られるようになります。 このように、2歳児は心身ともに成長が著しく日々の変化が大きい時期です。ただし、発達の順番やスピードは子どもによって異なるため、同じ月齢の子と比べて一喜一憂する必要はありません。 イヤイヤ期は親にとって大変な瞬間でもありますが、子ども自身の自立心や意思形成の表れでもあります。例えば「靴を自分で履きたい」「スプーンを持ちたい」と強く主張することも増えるでしょう。 親からすると手間に感じることもありますが、こうした経験を通じて自分でできたという達成感を積み重ねることが、将来の自信につながっていきます。 また、イヤイヤ期の特徴を事前に知っておくことで、2歳児の行動に振り回されず焦らず成長を見守ることができるでしょう。 ただし、これらの数字はあくまで中央値であり、子どもによって前後に幅があります。また、性別差よりも個人差が大きいことが特徴です。 成長曲線を大きく外れていない限り、過度に心配する必要はありません。 2歳0ヶ月から6ヶ月未満の男の子の中央値は86.0〜87.0cm、2歳6ヶ月から12ヶ月未満では90.5〜91.5cmが目安です。 2歳0ヶ月から6ヶ月未満の女の子の中央値は85.5〜86.5cm、2歳6ヶ月から12ヶ月未満では89.5〜90.5cmが目安です。 2歳0ヶ月から6ヶ月未満の中央値は12.0〜12.5kg、2歳6ヶ月から12ヶ月未満では13.0〜13.5kgが目安です。 2歳0ヶ月から6ヶ月未満の中央値は約11.5〜12.0kg、2歳6ヶ月から12ヶ月未満では約12.5〜13.0kgが目安です。 ここでは、2歳の子ができるようになることや家庭でチェックできる成長の目安を詳しくご紹介します。 2歳の時期は言葉の語彙が50語から200語ほどに増えるといわれています。二語文を話すようになる子もいるでしょう。「ママ、いく」「ブーブー、きた」などの簡単な文章で話すことが増え、自己表現ができるようになります。 まだ発音が不明瞭でも、親が繰り返し話しかけることで言葉の発達や理解が促されるでしょう。 ただし、言葉の発達には大きな個人差があり、まだ単語中心の子も少なくありません。焦らず見守ることも大切です。会話や読み聞かせを繰り返し、言葉の発達を支えていきましょう。 また、絵本や歌の内容を覚えて話したり、簡単なごっこ遊びをしたりすることが楽しめるようになります。「靴を持ってきて」「ここに座ろうね」といった簡単な指示を理解できるようになってきます。 また、着替えの際にはボタンを外すなどの細かい動作にも挑戦するようになります。 階段を片足ずつ上ることもでき、体全体を使った運動が活発になってきます。外遊びでの経験は、体力だけでなく協調性や注意力の発達にもつながります。 自分でできることが増える時期です。靴を履くこと、簡単な着替え、食事の準備の手伝いなどを通じて自立心が育まれます。 また、トイレトレーニングを始める家庭もありますが、こちらは個人差が大きいので焦る必要はありません。 積み木や簡単なパズル、ままごとなど、想像力を使った遊びが増えていきます。ごっこ遊びでは大人や友達の動作を真似ることで、言葉や社会性の発達にもつながります。 集中して遊ぶ力もついてくるので、そっと見守ることも大切です。 ママスクールでは、一生分の心・体・脳の土台づくりを叶えられるドーマンメソッドをベースにした親御さんが主体となって行うプログラムを提供しています。 無料セミナーを開催しており、そのセミナーではドーマンメソッドの一環として取り組まれているドッツカードを使用した実践方法をお話しています。 1日5分と遊び感覚でできるため、親も子も楽しみながら取り組むことが可能です。セミナーを聞いたあとすぐに実践できる内容もあるため、忙しいママも気軽に試すことができるでしょう。 ドッツカードやドーマンメソッドを日本で唯一、ドーマンメソッドを開発した博士と長年活動した先生が監修しているママスクールの無料セミナーで、子育ての軸を整えたい方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。 また、スクールの受講も効果的でしょう。0歳からのママスクールは世界中で10万人以上が効果を実感したドーマンメソッドをもとに、ママの子育て支援をするオンラインスクールです。 心・体・脳の3つを育むドーマンメソッドをベースに子どもの成長に不安感を持つことなく、ママが楽しく子育てができるような土台づくりができる環境やサポートを提供しています。 オンラインにて無料セミナーの開催しており、効果や進め方などを丁寧にお話しています。詳しく話を聞いてみたい方は、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。 言葉の理解力や語彙力を伸ばすために、親が絵本を読み聞かせることはとても効果的です。繰り返し出てくるフレーズや動物の名前を指差しながら教えることで、理解力も自然に高まります。 また、親子のスキンシップの時間としてとても大切なひとときになるでしょう。 子どもの発達を促すだけでなく気分転換にもなるので、体を使って遊ぶ時間を設けてみてはいかがでしょうか。 児童館や保育園の一時利用、親子サークルなどを活用し、同年代の子どもと触れ合う時間を持つことが社会性の発達につながります。 まだ協力して遊ぶことは少なくても、同じ空間で遊ぶ経験は社会性の発達にとても大切です。 ただし、言葉がまったく出てこなかったり、極端に感情表現が少なかったり、歩行が安定しないなど発達の遅れが気になる場合は専門機関に相談することが大切です。 ここでは、発達の遅れが気になる場合にできることをご紹介します。 2歳児の発達には幅があり、同じ月齢でも個人差が大きいこともあります。できないことが多少あっても、その子なりに成長していれば大丈夫ですので、心配しすぎる必要はありません。 とはいえ、ほかの子どもの行動が目に入ると、つい比べて焦ってしまうかもしれません。焦らず、発達を促す行動をしながら温かく長い目で見守りましょう。 2歳児の発達にどうしても強い不安を感じる場合は、市区町村の保健センターで実施される健診や発達相談の窓口、小児科や発達外来に相談することができます。 発達外来や専門家に相談することで、必要に応じて療育や発達支援に早くつなげることが可能です。自分が住んでいる地域ではどのようなサポートがあるのか調べてみるとよいでしょう。 また、同じ悩みを持つママたちともつながれるオンラインスクールに参加するのもひとつです。 ママスクールは、ママの心を豊かにし楽しみながら子育てができる独自のコンテンツやサポートをそろえています。 オンラインコミュニティでは、全国のママと交流できるため、心の内を相談することが可能です。同じ悩みを持つママや先輩ママからのアドバイスや意見ももらえるため、心強い存在といえるでしょう。 1人で悩まず、子育ての専門家に悩み事を相談してみませんか。無料セミナーで、問題解決の糸口を見つけられるかもしれません。 2歳児の発達は一律に比較せず、無理に練習を強いることは避けるのが望ましいでしょう。例えば「今日はジャンプができるかな?」「まだ言葉が増えないのは大丈夫かな?」と心配になることもあるかもしれません。 しかし、昨日よりもできたことや、挑戦しようとする姿勢に目を向けてあげることが自己肯定感を育む大切な土台になります。 また、幼児期にはできたことをほめることや不安の少ない環境を与えることが健やかな発達につながるとされています。親の焦りが伝わると、かえって自信を失わせてしまう場合があるので、余裕を持って関わる姿勢が大切です。 さらに、2歳児は模倣の力が強まるため、親の行動や言葉を真似しながら学んでいきます。親が楽しそうに家事をしていれば子どもも自然に「やってみたい」と思い、生活習慣の練習につながります。 特別な教材や習い事を用意しなくても、食事の準備や片付け、着替えといった日常生活そのものが学びの場になるでしょう。 このように、日々の関わり方次第で子どもの発達を大きくサポートできるため、親自身が完璧を求めすぎず「楽しく一緒にやってみよう」という姿勢でいることが大切です。 生活のなかで、子どものやってみたいという気持ちを尊重することが学びにつながるのです。 とはいえ、「どんな方法で子どものやってみたい気持ちを伸ばすことができるのだろうか」と迷っているママもいるかもしれません。そんなときは、子どもの可能性を伸ばしてくれるママスクールがおすすめです。 ママスクールでは、0歳からの一生分の土台づくりを叶えるドーマンメソッドや、日本唯一の正規ドッツカード教材をはじめ、ママの心を支えるコミュニティや専門家と直接相談できる機会のある相談会など、楽しみながら子育てができる環境が整っています。 無料セミナーでは、ドッツカードの正しい使い方をはじめ、本質的な子育てのお話をしてくれます。 この機会に、ぜひあなたの子育てが変わるきっかけを見つけてみませんか? しかし、言葉がなかなか出てこない、周囲との関わりが極端に少ない、動作のぎこちなさが目立つなど不安に感じる場面が続くと心配になることもあるでしょう。 子どもの発達に関して気になることがある場合には、早めに専門家に相談することも大切です。市区町村の保健センターでは、1歳半健診や3歳児健診の間に心配があれば、随時発達相談を利用できます。 早期に発達支援の専門機関とつながることで、必要に応じて療育や発達支援を受けられ、子どもに合ったサポートにつながります。 また、発達相談を受けることは、子どもだけでなく保護者にとっても大きな意味があります。自分の見立てだけで不安を抱え込むのではなく、客観的な視点から評価を受けられることで、不安なく子どもの成長を見守れるようになるかもしれません。 さらに、必要に応じて地域の子育て支援センターや児童発達支援事業所とつながることで、家庭だけでは得られない学びや経験を子どもに提供することが可能になります。 不安を減らせる環境を整えることは、子どもだけでなく親自身の精神的な支えにもつながります。 ママスクールでは、0歳からの育児や子どもの発達に合わせた遊びや関わり方などを提供する無料セミナーを開催しています。 セミナーでは専門家の知見に基づいた話を聞けるだけでなく、子育てに悩みを抱えつつも、今は「育児が楽しくなった!」「子どもの可能性を伸ばせて嬉しい」というママさんから実際の体験談も聞くことができます。 同じような境遇だったママさんの話を聞くことで、「悩んでいるのは私だけじゃないんだ」と思うことができるかもしれません。 また、家庭でできる実践方法を学ぶことで、日々の育児に自信を持つことができるので不安なく子どもの成長を見守ることができるようになるでしょう。 ママスクールに参加した方のなかには、「家庭で取り入れやすい工夫を学べた」「不安が軽くなり、子どもと向き合う時間が楽しくなった」といった声も寄せられています。 子育ての情報はインターネットや本でも得られますが、専門家に直接質問できる機会はとても貴重です。 子どもの発達に関して気になることがある方は、まずは無料セミナーに参加して、一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
「同じくらいの月齢の子がもうおしゃべりしているのに、うちの子はまだ単語しか出ない……」「ほかの子は走り回っているのに、うちの子はまだよちよち歩きで大丈夫だろうか……」など、子どもの成長は日々の喜びであると同時に不安の種にもなります。2歳児の特徴は?

2歳になるとだんだんと赤ちゃんの面影が薄れていき、表情やしぐさに子どもらしさが出てきます。体力や好奇心、感情表現が急速に発達するため、毎日の成長に親は驚かされることもあるでしょう。2歳児の身体の発育

2歳になると体の成長も大きな変化が現れる時期を迎えます。成長のスピードには個人差がありますが、ここでは2歳児の平均的な身長や体重の中央値をご紹介します。男の子の平均身長
女の子の平均身長
男の子の平均体重
女の子の平均体重
2歳になるとできることや発達の目安

2歳になると言葉や理解力、運動、生活、社会性、遊びなどのあらゆる面で大きな成長が見られます。言葉の発達
理解力や記憶力の向上

2歳になると日常生活の流れを覚える力が育っていきます。例えば食事の前に手を洗う、着替えを自分でする、外出前に靴を持つなどの行動を自分から進んで行う子もいます。身体の発達

手先の器用さが増してくるので、積み木を3つ以上重ねたりクレヨンで描いたりすることができるようになります。食事の際はスプーンやフォークを使って自分で食べようとする意欲も芽生えます。運動能力の発達

歩くだけでなく走ったりジャンプしたりする動作が増え、ボールを投げたり蹴ったりすることもできるようになります。生活
社会性

同年代の子どもへの興味が強まり、同じ空間で遊ぶ平行遊びが中心となります。協力して一緒に遊ぶようなことは少ないですが、友達の存在を意識すること自体が社会性の芽生えです。遊び
2歳児の発達を促す関わり方

2歳児の発達には大きな個人差があるといわれていますが、家庭での関わり方が発達を促すうえで重要です。絵本の読み聞かせをする
身体を使った遊びをする

外遊びや室内での体を使った遊びは、運動能力や情緒の発達を促します。公園で走る、ジャンプをする、ボール遊びをすることはもちろん、新聞紙を丸めて投げる、段ボールで迷路を作るなど家庭内でも十分に楽しめることもたくさんあります同年代の友達と遊ぶ機会をつくる
発達の遅れが気になる場合の対処法

2歳児の発達には大きな幅があるため、ちょっとした違いで心配しすぎる必要はありません。焦らず長い目で見守ることも大切です。焦らずに見守る
支援機関や医療機関に相談する
2歳児との関わりの注意点

2歳児は自分でやりたい気持ちが強くなる一方で、思い通りにいかないと感情的になりやすく、いわゆるイヤイヤ期を迎える時期です。発達には大きな個人差があるため、親が焦らず子どものペースを尊重することがとても大切です。2歳児の発育や発達が気になるなら

子どもの発達のペースは一人ひとり異なるため、同じ月齢でもできることや興味の対象に差があるのは自然なことです。