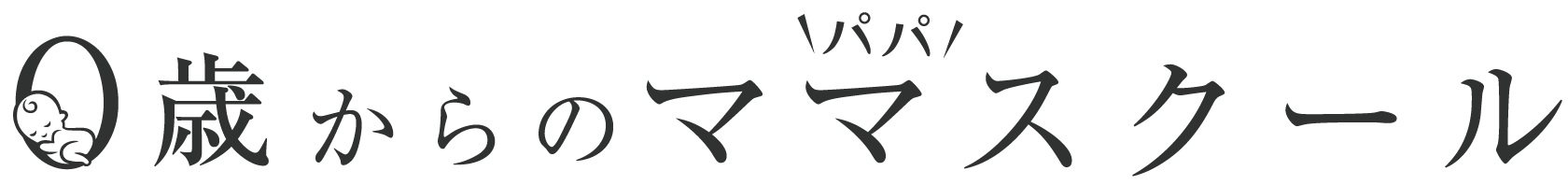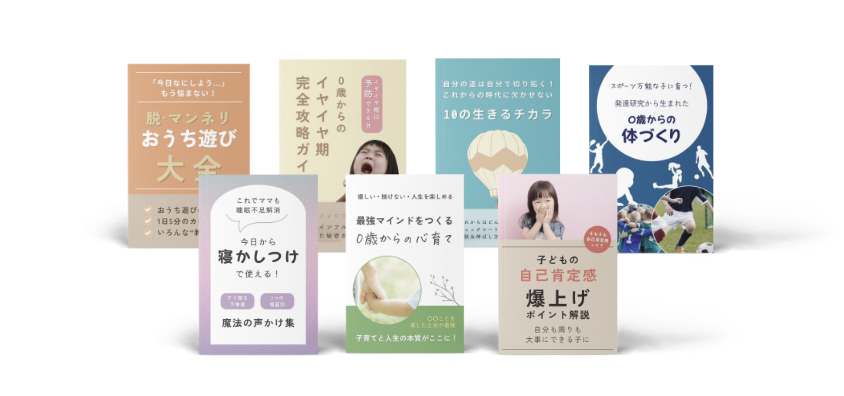1歳代でイヤイヤ期が始まることもある?対処法や接し方の注意点、乗り越え方を解説
イヤイヤ期は自我が芽生えて、自分でやってみたい気持ちが出てくると、自然にイヤイヤ期が始まります。 そのため、1歳前後で始まるお子さんも少なくありません。 この記事では、イヤイヤ期が始まる時期や子どもへの上手な対応、辛いイヤイヤ期を乗り越える方法などについて紹介します。 頭を抱えてしまうイヤイヤ期を上手に乗り越えて、親子の信頼関係を深めていきましょう。 目次 早いお子さんでは、生後6ヶ月頃から自我が芽生え始めて、イヤイヤ期の兆候が見られるケースもあります。 イヤイヤ期は、子どもの成長過程の一つです。そのため、個人差があります。 一般的な年齢よりも早くイヤイヤ期を迎えると不安を感じてしまいますが、それもお子さまの個性なので、受け入れてイヤイヤ期を乗り越えましょう。 イヤイヤ期は、子どもの自我が芽生え始め、順調に成長している証です。 この頃には、お子さんが急成長し、「自分で服を着てみたい」「自分で靴を履いてみたい」などの自己主張の気持ちでいっぱいになります。 しかし、やりたい気持ちを言葉で表現することが難しく、自分のやりたいことができずに「イヤ」という言葉で表現して泣き叫ぶ行動につながるのです。 また、イヤイヤ期は意思表示をする練習期間でもあります。 子どもは、親のいうことに対してイヤと否定したいわけではなく、「自分でやりたいのに!」「自分でできるのに!」という気持ちが込められています。 そのため、「自分でやりたいの?」「自分でお洋服着てみる?」などと子どもの気持ちを受け止めて、言葉で気持ちを表現してあげましょう。 子どもの気持ちを代弁してあげることで、感情や気持ちを表現する術を学んでいきます。 ここでは、イヤイヤ期が始まったときの上手な対処法を紹介します。子どもが「イヤ」という意味を理解して、対処したり一緒に解決することが大切です。 イヤイヤ期は、子どもが自分の気持ちや意思を言葉で表現することができずに、「イヤ!」という言葉で気持ちを伝えています。 何でもかんでも「イヤ!」といっているのではなく、理由があって表現しているので、何が嫌なのかを考えて「これが嫌なの?」「自分でやりたかったの?」というように子どもの気持ちや意思を言葉で伝えてあげましょう。 子どもの気持ちを代弁し、「そうだね」と共感することで、気持ちを理解してもらえたと安心感を得られるでしょう。 また、気持ちを代弁することで感情の名前を覚え、気持ちを伝える練習ができるため、少しずつ自分の気持ちや意思を伝えられるようになります。 「イヤ」といわれても否定をせずに、受け入れて理解する姿勢を示すことが重要です。 時間がないとなかなか子どものやりたい気持ちを尊重できないことがありますが、何でもママが先回りしてやってしまうと、子どものチャレンジ精神を妨げてしまう恐れがあります。 子どもが自らやりたいという意思表示が見られた場合には、気持ちを尊重してチャレンジさせ、自立心やチャレンジ精神を育てていきましょう。 もし、子どもに任せるのが不安というママは少し手伝いながらでもよいので、子どもが自分でできたという達成感を経験させてあげることが成長につながります。 イヤイヤが落ち着かないときや癇癪を起こしてしまった場合には、落ち着くまで静かに見守ることも必要です。 イヤイヤ期には、自分でやりたいという気持ちのほかに、自分のペースでやりたいという気持ちも込められています。 ママに早くしてと急かされたり、ママが先にやってしまったりするとイヤイヤが起こってしまうため、「ママ待っているから自分でやってみようね!」と声かけを行いましょう。 イヤイヤが落ち着くと、「気持ちが落ち着くまで待ってくれた」という安心感につながります。 早くしてほしいというママの気持ちもあるので、時間に余裕を持った行動を心がけましょう。 公園や外出先で、「まだ帰りたくない」「まだ遊びたい」という気持ちになった場合は、興味を別のことに向けてみましょう。 「お家に帰ったら好きなおもちゃで遊ぼう」といってみたり、「お家まで競争しよう」など、一緒に楽しめる提案をしてみましょう。 帰りたくない気持ちや遊びたい気持ちを受け止めてから、別の楽しい提案をして気持ちの切り替えを行うことも大切です。 イヤイヤモードのときには、なにかお願いしたりやってほしいことを伝えても「イヤ!」といって、指示を受け入れることが難しい状況になっています。 そのため、子どもにしてほしいことがある場合は、ポジティブな言葉に変換して伝えてみましょう。 例えば、「お着替え何秒でできるかな?」と伝えてみたり「お風呂までママと競争しよう!」といってみたり、子どもがワクワクするようなポジティブな声かけに変換することで子どものモチベーションアップにもつながります。 子どもに何をいっても「イヤ!」という場合には、自分で選択したい気持ちが芽生えています。 例えば、「今日の服は緑と青どっちにする?」と聞いてみたり「お風呂はご飯の前と後どっちにする?」など、自分で選べるような選択肢を用意しておきましょう。 また、子どもに選んでもらう場合には「今からお着替えする?」というように選択できないものは避けて、2個か3個の選択肢を用意しましょう。 また、選択肢を用意する際には子どもがどれを選んでも困らない選択肢を用意しておくことも大事です。 選択をしてもらうことで、子どもがスムーズに行動してくれたり、自立心を育てたりすることができます。 一時的な感情で、子どもにあたってしまうと親子の信頼関係に傷をつけることになるので注意が必要です。 ここでは、イヤイヤ期の子どもへの接し方について紹介します。イヤイヤ期の子どもに接するときの注意点を理解しておきましょう。 毎日のように子どもが「イヤ!」と否定すると、親はどうしても「ダメ」と言いたくなりますが、頭ごなしに否定してはいけません。 ただ、「ダメ!」といってしまうと、子どもは否定されたと感じて自己主張や意思表示をする機会を失ってしまう可能性があります。 ダメという場合には、ダメな理由や意味を説明するように心がけましょう。 子どものイヤイヤに毎日付き合っていると、自然と心が荒れてしまいます。イヤイヤ期も楽しく過ごし、よい思い出として残せるようにママ自身が心に余裕を持つことが大切です。 また、イヤイヤ期でも楽しく教育してあげたいと思っているママたちもいることでしょう。 親に無視されると、子どもは気持ちを無視されたと感じて、不安や絶望を抱いてしまう可能性があります。 もし、子どものイヤイヤが激しくてなかなか落ち着かないときは、少し離れて様子を見守ってみましょう。 落ち着いてきたら、子どもの気持ちを代弁し共感してあげることで、理解してもらえたと安心感を抱くことでしょう。 服を着てくれなかったり、保育園に行く準備をしてくれなかったりしないと、どうしても先回りをしてやってしまいたくなります。 しかし、先回りして何でもやってしまうと子どもが自らやりたいという気持ちをなくして、自分の気持ちを表現する機会が失われてしまいます。 子どもの「自らやりたい」という気持ちを理解し受け止めてあげて、やりたいことを見守ったり一緒にやったりして、やりたい気持ちを優先してあげましょう。 感情的になって、子どもに怒りをぶつけると恐怖心を抱いてしまい、子どもとの信頼関係に悪影響をもたらす危険があります。 感情的に怒られたり怒りをぶつけられたりすることに慣れてしまうと、親の様子を伺うようになったり、自分の感情を押し殺してしまう子に育つケースも少なくありません。 イライラした場合には、少しママの時間を確保してリフレッシュしたり、子どもから離れて気持ちを落ち着かせるようにしましょう。 子どもに「イヤ!」とばかりいわれてイライラしても、脅すようないい方は避けるようにしましょう。 「置いていくよ」や「先に帰るから勝手にして」など子どもを脅すようないい方をすると、一時的にいうことを聞いてくれますが、恐怖心を抱くことにつながります。 ダメな理由を言葉や行動で伝えて、理解してもらえるように工夫をしましょう。 また、脅していうことを聞かせてしまうと、成長したときに友達や仲間を脅していうことを聞かせようとするケースもあるので注意が必要です。 0歳からのママスクールでは、ママが幸せに楽しく育児ができる土台づくりを目指しております。 育児の悩みを専門家に直接相談できる子育て相談会や、ほかのママと交流できるオンラインコミュニティなどが用意され、情報交換を行いながらお互いに支えあえる環境が整っています。 また、世界100ヶ国以上の赤ちゃんの脳の発達を50年以上研究して誕生したママがおうちで1日5分で0歳から心・体・脳を育めるドーマンメソッドの知識を学ぶことも可能です。 イヤイヤ期の子どもへの関わり方に悩んでいるママや乗り越え方がわからないママは、まずは無料セミナーに参加してみませんか? ここでは、イヤイヤ期を乗り越えるためのヒントを紹介します。ママ一人で抱え込まず、上手に乗り越える方法を見つけましょう。 イヤイヤ期は、子どもが小さい身体でめいっぱい成長している段階です。 「イヤ!」といえるのは、それだけ自分の意思があること、自分の気持ちを伝えたいと感じているということです。 イヤイヤ期は子どもの気持ちを理解できるチャンスや成長している証だと、前向きに受け止めてみましょう。 また、子どもの成長をしっかり受け止めるためにもママの気持ちに余裕が必要です。子どもがイヤイヤと言っても問題ないように、時間に余裕のある行動をすることもおすすめです。 パートナーや親、兄弟や友人などに少し手伝ってほしいと伝えてみましょう。 できるだけ一人で抱え込まず、可能な範囲で周囲に頼ることもイヤイヤ期を乗り越える大事な方法です。 なかなか周囲には頼みにくい場合には、保育園や幼稚園・ベビーシッター・託児所などのサービスを利用するのもおすすめです。 ママスクールでは、ママ同士のオンラインコミュニティがあるため、育児の情報交換や悩みを共有できます。 お互いを支えあえる環境が整っているので、孤独になりやすい子育て期間でも「私だけじゃない」と前向きな気持ちになれます。 また、専門家に直接相談できる子育て相談会もあるため、プロの知識やアドバイスを得られる点もメリットといえるでしょう。 イヤイヤ期に悩みがあるママや誰かに相談したいママは、ぜひ一度ママスクールに相談してみませんか。 まずは無料で開催しているオンラインセミナーでお待ちしています。 イヤイヤ期に疲れてきたら、リフレッシュできる時間を確保しましょう。 好きなことや趣味があれば没頭する時間を作ったり、少し身体を動かして汗をかいてみたり、思いっきり寝てみたりと、ママが好きなことをして自分の時間を作ることが大切です。 リフレッシュがうまくできてママの気持ちの余裕があれば、イヤイヤ期の我が子を受け止めて、しっかりと向き合えるようになります。 同じ悩みを持つママ同士で情報を共有したり交換したりすることも、イヤイヤ期の乗り越え方のひとつです。 イヤイヤ期の子どもを持つママは、イヤイヤに対する対処法や上手な気分転換の方法など、自分では思いつかなかった方法を実践している場合があります。 また、周囲に気軽に相談できるママ友がいない場合には、インターネットやSNSのコミュニティに参加してみるのもおすすめです。 0歳からのママスクールでは、同じ悩みを持つママとの情報交換や情報共有ができるオンラインコミュニティがあります。 いつでもオンラインチャットができる環境やZoomお茶会の開催があり、一人で抱え込んでしまうママも気軽に参加しやすい環境が整っています。 また、オンラインコミュニティでは運営から公式に認定された信頼できるサポートママさんからの返信もあり、安心感を持って相談が可能です。 イヤイヤ期の子育てに悩んでいるママは一度、ママスクールに相談してみませんか。 まずは無料セミナーで子育てがもっと楽しくなる方法を知ってみてください。 イヤイヤ期は、1歳半から2歳頃に始まるお子さんが多く、2歳頃にピークを迎えます。3歳頃から徐々に落ち着き始めて、4歳頃には終わるといわれています。 ただ、イヤイヤ期が始まる年齢には個人差があるので、1歳頃から始まり4歳まで続くケースもあることを理解しておきましょう。 ママスクールでは、ママが幸せに子どもの人生の土台づくりができる場所をモットーに、育児メソッドを提供しています。 心・体・脳の3つを育むドーマンメソッドを取り入れ、子どもが自ら学んで人生を楽しめるような土台づくりができる育児をしていくことが可能です。 どんなママでも1日5分で気軽に実践できて、遊び感覚で子どもの可能性を伸ばせるドッツカードの魅力や具体的な方法もお伝えしています。 ママが楽しみながら育児ができる土台づくりの知識を学んでみませんか? イヤイヤ期の始まりには、個人差があるため、1歳前後で始まっても心配することはありません。ただ、毎日「イヤ!」といわれ続けるとママの気力が続かなくなってしまうことでしょう。 もし、イヤイヤ期のお子さんに手を焼いているならプロの力を借りてみませんか。 ママスクールでは、ドーマンメソッドをもとにした0歳から始める子どもの土台づくりの方法を知識ゼロから学ぶことができます。 ママが幸せに育児をしながら子どもの土台づくりができる環境が整っているので、楽しんで育児をしたり子どもの成長を見守ったりすることが可能です。 また、専門家による子育て相談会で育児の知識を学んだり悩みを相談したりできるので、楽しく子育てができるようになっていきます。 オンラインで相談会に参加したりサポートを受けたりできるので、どのような状況のママでも安心感を持って相談できる環境が整っています。 子育てやイヤイヤ期に悩んでいるママは、ママスクールの無料セミナーに参加して、イヤイヤ期を乗り越えるヒントを見つけてみませんか。
1歳前後なのに「イヤ」という回数が増えたり、親のいうことを否定するようになったりすると「もうイヤイヤ期が始まったの?」「ほかの子よりも早くて不安」と感じているママも少なくないでしょう。イヤイヤ期はいつから始まる?

イヤイヤ期が始まるのは、一般的に1歳半から2歳頃です。2歳頃にピークを迎えるといわれています。1歳代でイヤイヤ期が始まることもある?

イヤイヤ期が早くスタートすると不安を感じてしまいますが、個人差があるものなので、1歳前後で始まることもあります。子どものイヤイヤが始まったときの対処法

毎日「イヤイヤ!」といわれると、どう接していいのか、どのような声かけをしたらいいのかわからなくなります。子どものイヤな気持ちを言葉にしてあげる
ある程度子どもの好きなようにさせる

イヤイヤ期の子どもは、自分でやりたいという気持ちがあります。イヤイヤが落ち着くまで静かに見守る
ほかの楽しいことで興味をそらす

ほかの楽しいことで興味をそらすことも対処法の一つです。ポジティブな声かけを心がける
選択肢を用意して自分で決めさせる
イヤイヤ期の子どもへの接し方の注意点

「イヤ!」と一方的に否定されると、ママもイライラして、つい感情的になってしまうことも多いでしょう。子どもを否定しない
子どもを無視しない

子どものイヤイヤが激しいときでも、子どもを無視するような行動は取らないようにしましょう。先回りして手伝いすぎない
子どもに怒りをぶつけない

イライラしても子どもに怒りをぶつけないことも大事なことです。脅していうことをきかせない
イヤイヤ期の乗り越え方は?

イヤイヤ期は、親にとって大変な時期です。毎日毎日「イヤ!」と言われ続けると、親もストレスが溜まりイライラしてしまうものです。これも成長の証だと前向きに受け止める
可能な限り周囲に頼る

イヤイヤ期は、ストレスを感じやすく育児に自信がなくなりやすくなる時期です。一人で抱え込むと辛くなってしまうので、周囲を頼ってみましょう。リフレッシュできる時間を作る
同じ悩みを持つ方と情報共有をする
イヤイヤ期はいつまで続く?

毎日「イヤ!」と言われると、親もイヤになってきて早くイヤイヤ期が終わることを願っているママもいることでしょう。1歳代の子どものイヤイヤ期に手を焼いているなら

イヤイヤ期は、子どもの自立心や意思表示を身につけるために大事な成長過程です。